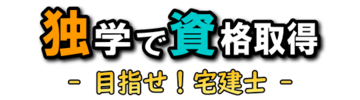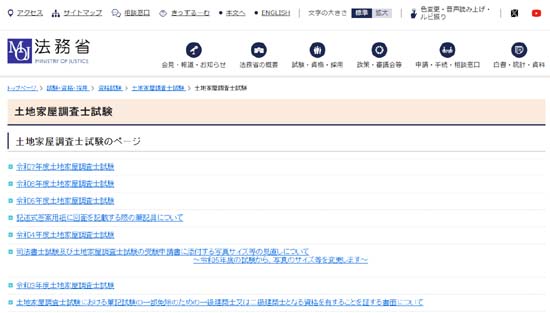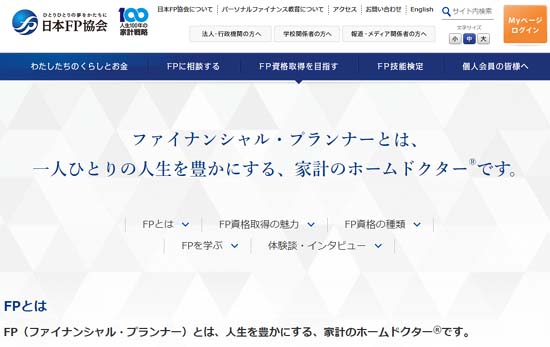宅建からダブルライセンスに挑戦しよう!次に取る資格おすすめ8選
更新日:2026年2月12日
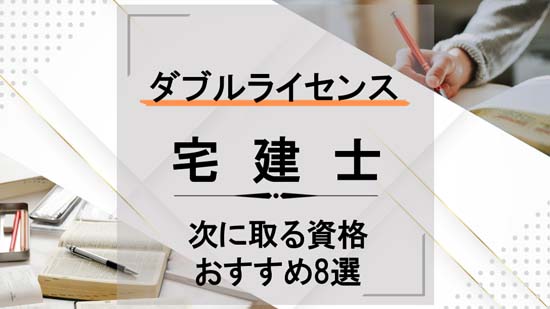
宅建は、不動産資格の筆頭資格であり、法律資格の登竜門とも言われる資格です。
このため、宅建に関連する資格は数多くあり、宅建を取得することで、次から次へと広がりを見せてくるため、ダブルライセンス・トリプルライセンスへの挑戦意欲も沸いてきますね!
実務上も、資格を増やすことでお客様からの信頼が得られるのはもちろん、同僚・上司からの評価も上がりますし、転職や独立といった新たなビジネスチャンスも生まれてきます。
このページでは、宅建と一緒に持っておくと良いダブルライセンス・トリプルライセンスにおすすめの資格について、私自身の経験も踏まえて紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
|
【執筆者】 |
執筆者紹介 |
宅建からダブルライセンスに挑戦しよう!

宅建の次に取る資格として、ダブルライセンス・トリプルライセンスを目指す場合、どんな資格が候補に挙がってくるのでしょうか。
宅建は、不動産資格の筆頭資格であることから、やはり不動産資格との相性がいいですね。
また、法律資格の登竜門でもあるため、不動産業と合わせて独立できる士業資格にステップアップすることも視野に入ってきます。
そして、業務内容の関連性からは、営業に役立つ金融・労務系の資格も候補に挙がります。
- 相性のいい不動産資格・・・管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション管理士
- 独立できる士業資格・・・司法書士 、土地家屋調査士(測量士補) 、行政書士
- 営業に役立つ金融・労務資格・・・ファイナンシャル・プランナー、社労士
相性のいい不動産資格
宅建と相性がいいのは、やはり不動産資格です。
不動産4大資格と呼ばれる宅建、管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理士は、一緒に持っておくと良いですね。
管理業務主任者は分譲マンションの管理業務、賃貸不動産経営管理士は賃貸マンションの管理業務、マンション管理士は分譲マンションのコンサルティングの専門家です。
これらの資格は、不動産の仕事をするうえで密接に関連しますので、いま不動産業界で働いている方は、ぜひチャレンジしたい資格です。
また、試験範囲も共通する科目が多いので、取得しやすい資格でもあります。
独立できる士業資格
宅建と合わせて取ることで、不動産業と一体的に独立できる士業資格もあります。
士業の資格でおすすめは、司法書士・土地家屋調査士・行政書士です。
不動産を売買すれば、所有権移転登記や抵当権設定登記をするのは司法書士なので、不動産を売った際に、司法書士として自ら登記することが可能です。
また、家を新築すれば土地家屋調査士が表題登記をしますし、宅地を分譲・開発する際にも、分筆登記や地目変更登記をしますので、それらを土地家屋調査士として自ら登記することができます。
さらに、農地(田・畑)を売買する場合は農地法の許可が必要ですし、不動産を売買(又は賃貸)した後に、飲食店や旅館業、建設業など各種の許認可申請が必要な場合は、行政書士として自ら許認可申請をすることができます。
このような士業の資格は、宅建と合わせて独立開業したい方におすすめですね。
なお、試験範囲も、司法書士・土地家屋調査士・行政書士とそれぞれ共通する科目もあります。
営業に役立つ金融・労務資格
不動産の営業に役立つ資格として、金融・労務系の資格があります。
金融・労務資格でおすすめなのは、FP(ファイナンシャル・プランナー)と社労士(社会保険労務士)です。
不動産という大きな買い物をするうえで、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナーや、年金・社会保険の専門家である社労士といった専門知識を身につけることで、お客様の資金計画やライフプランの側面からアドバイスできるようになります。
特に、FPは、宅建の試験範囲と重複する部分が多くありますので、おすすめですね。
私が取得した資格・今後取得を目指す資格
私自身は、公務員として市役所に勤めながら、一番最初に宅建を取得したあと、土地家屋調査士・測量士補、行政書士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士と、順に資格試験に挑戦してきました。
そして、市役所を辞めて司法書士試験に合格し、事務所を開業したあと、簿記3級・2級、FP3級・2級・1級、そして社労士を取得しました。
私は22年間、公務員として市役所に勤めていたので、基本的には終身雇用を考えていましたが、万が一退職せざるを得ない状況になったとしても対応できるように、そしてまた、時と場合によっては自ら仕事を辞めて資格を活かして働いてみたいという思いを心の片隅に持っていました。
もちろん、定年退職後の再就職に活かすこともできるという考えもありました。
ただし、ただの資格マニアのように見境なく資格試験に挑戦してきたわけではなく、職務上、必要だと感じたからこそ資格の勉強をしたというのが実状です。
市役所で働く公務員に、どうして資格が必要なのかと疑問に思うかもしれませんが、市役所の仕事は多岐にわたっています。
一般の事務職であっても、建築・土木の部署や不動産の部署、法務や税務、会計など、どんな部署にでも3~5年ごとに異動させられます。
このため、少なくとも、法律・不動産・会計の資格ジャンルは、すべてが市役所の業務に直接的に関連する資格と言えるわけです。
不動産資格四冠?転職・独立を目指す?視野・得意分野を広げる?
では、話を戻すと、ダブルライセンス・トリプルライセンスを目指す場合、考え方はいくつかあります。
不動産資格四冠を目指す?
宅建業に従事されている方が、最初に宅建を取得した後、ダブルライセンス・トリプルライセンスを考える場合は、不動産資格を極めるため、宅建・管理業務主任者・マンション管理士のトリプルライセンス、もしくは、賃貸不動産経営管理士の4大資格まで目指すのが順当なところではないでしょうか。
この4つの資格を揃えれば、「不動産資格四冠」と呼ばれるため、職場において一目を置かれる存在になれますし、お客様からの信頼も高まりますね。
転職・独立を目指す?
あるいは、転職や独立を目指して、司法書士や土地家屋調査士・行政書士といった、自分で看板を掲げられる資格を目指すのも、考え方のひとつかもしれません。
視野・得意分野を広げる?
または、視野を広げて得意分野を拡大するために、少しジャンルの異なるファイナンシャル・プランナーや社労士を目指すのも、いいかもしれませんね。
宅建の次に取る資格おすすめ8選
それでは、宅建の次に取るべきダブルライセンス・トリプルライセンスが目指せる資格について、おすすめ順に紹介していきたいと思います。
No.1:管理業務主任者
宅建とのダブルライセンスの候補として筆頭に上がってくるのが、この管理業務主任者ではないでしょうか。
不動産会社に勤める方にとっては、業務と直接的に関わりますし、試験科目も宅建に共通する部分が多くあります。
まず、民法と区分所有法は、がっつりと被ります。その他、出題数は少ないですが、借地借家法・宅建業法・不動産登記法といった法律も、共通する科目として挙げられますね。
管理業務主任者とは
管理業務主任者は、マンション管理のエキスパートとして、マンションの管理業務を行う国家資格です。
マンション管理業者は、管理を受託する管理組合の数に応じて、30管理組合ごとに1名以上の「管理業務主任者」を設置することが義務付けられています。
また、この管理業務のなかには、管理業務主任者にしかできない4つの独占業務があるため、管理業務主任者は、マンション管理業務になくてはならない非常に重要な役割を担っています。
資格の取得方法
管理業務主任者になるためには、1年に1回実施される管理業務主任者試験に合格した後に、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受ける必要があります。
この登録を受けるには、マンション管理の実務経験が2年以上あること、又は、2日間の登録実務講習を受講すること等が要件とされています。
試験科目
四肢択一(マークシート) 50問
| 分野 | 主な科目 | 出題数 |
|---|---|---|
| 法令系科目 | 民法、その他法令 | 10問 |
| 区分所有法 | 7問 | |
| マンション標準管理規約 | 6問 | |
| マンション管理適正化法 | 5問 | |
| 管理実務・会計系科目 | 管理実務・会計 | 9問 |
| 建築、設備系科目 | 建築、設備 | 13問 |
試験日程
例年、12月の第1日曜日に実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、初心者が管理業務主任者試験に合格するためには、300時間の勉強時間が必要と言われています。
1日に1~2時間の勉強時間なら、半年間程度が標準的な学習期間になってきます。
ただし、私の経験上は、宅建試験の合格者なら、初心者の3分の1ぐらい(100時間)の勉強時間があれば、十分合格できるのではないかと思います。(私も、約80時間の勉強時間で合格できました。)
難易度・合格率
受験者数は約1万5千人で、合格率は20%程度で推移しています。
国家資格としてはそれほど高くない難易度ですね。
No.2:賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、2020年度までは民間資格(公的資格)でしたが、2020年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立し、2021年4月21日付けの国土交通省令により、2021年度から国家資格になりました。
宅建を取得した方がダブルライセンス、トリプルライセンスを目指す資格として、管理業務主任者・マンション管理士と並んで候補に挙がってくる資格ですね。
賃貸不動産経営管理士とは
賃貸不動産経営管理士は、賃貸マンションや賃貸アパートなど、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸マンションやアパートなどの賃貸管理業務は、賃貸不動産の管理を家主から受託する契約から始まり、入居者の募集や契約業務により希望者を入居させ、建物の維持管理や不具合の対応、原状回復工事など様々な業務があるほか、家主の賃貸経営に関する支援もその業務の一環と捉えられています。
資格の取得方法
年に1回実施される賃貸不動産経営管理士試験に合格した後に、登録手続を行うことで、賃貸不動産経営管理士に認定され、賃貸不動産経営管理士証の交付を受けることができます。
この登録を受けるためには、賃貸不動産関連業務の2年以上の実務経験があること、又は、実務経験がない場合は「実務講習」を受講すること、のいずれかの要件を満たす必要があります。
試験科目
四肢択一(マークシート) 50問
| 試験科目 | 出題内容 |
|---|---|
| イ 管理受託契約に関する事項 |
管理受託契約の締結前の書面の交付、管理受託契約の締結時の書面の交付、管理受託契約における受任者の権利・義務、賃貸住宅標準管理委託契約書 等 |
| ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項 |
建築物の構造及び概要、建築設備の概要、賃貸住宅の維持保全に関する管理実務及び知識、原状回復 等 |
| ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項 |
家賃、敷金、共益費その他の金銭の意義、分別管理 等 |
| ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項 |
賃貸借契約の成立、契約期間と更新、賃貸借契約の終了、保証、賃貸住宅標準契約書、サブリース住宅標準契約書 等 |
| ホ 法に関する事項 |
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン、特定賃貸借標準契約書 等 |
| へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項 |
賃貸不動産の管理業務を行うに当たり関連する法令、賃貸不動産管理の意義と社会的情勢、賃貸不動産経営管理士のあり方、入居者の募集、賃貸業への支援業務 等 |
試験日程
例年、11月の第3日曜日に実施
合格に必要な勉強時間
一般的には、初心者が賃貸不動産経営管理士試験に合格するためには、200時間程度の勉強時間が必要と言われています。
1日に1~3時間の勉強時間なら、3ヶ月~6ヶ月程度が標準的な学習期間になってきます。
ただし、宅建試験や管理業務主任者試験の合格者なら、半分程度(100時間)ぐらいの勉強時間があれば十分合格できると思います。(私も、33時間の勉強時間で合格できました。)
難易度・合格率
受験者数は3万人を超え、増加傾向にあります。
合格率は、もともと50%程度で推移していましたが、国家資格化に向けた動きの中で、2019年度は36.8%、そして2020年度は29.8%にまで下がり、国家資格となった2021年度は31.5%と下げ止まり、その後もおおむね30%程度で推移しています。
No.3:マンション管理士
マンション管理士は、管理業務主任者と試験科目がほぼ共通していることから、管理業務主任者と並んで、宅建のダブルライセンス候補になってくる資格です。
資格名の響きから、管理業務主任者よりなんとなく格好いいですし、世間の認知度も管理業務主任者より高い印象があります。
ただし、不動産業界で働くうえでの必要性からいうと、管理業務主任者の方が上なんでしょうね。管理業務主任者には独占業務がありますが、マンション管理士にはありませんから。
マンション管理士とは
マンション管理士は、マンション管理組合や区分所有者から相談を受け、マンションに関する高度な専門知識をもって指導やアドバイスを行うことを業務としています。
相談には、管理組合の運営や管理規約の改正、大規模修繕工事などマンション管理に関する様々な問題があり、マンション管理士は、ひとことで言えば、マンション管理のコンサルタントといえます。
マンション管理士は、「名称独占資格」と言われ、宅建士や管理業務主任者のような独占業務はありません。
また、業者への設置義務もありませんが、資格を保有することで、マンション管理会社においてアドバイザーとして信頼度が上がることや、コンサルタントとして独立開業することも可能な資格です。
資格の取得方法
マンション管理士になるためには、年に1回実施されるマンション管理士試験に合格した後に、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。そして、登録を受けるとマンション管理士登録証が交付されます。
なお、マンション管理士の登録を受けるに当たっては、宅建士や管理業務主任者とは違って、実務経験や登録実務講習などは必要とされていません。
試験科目
四肢択一(マークシート) 50問
| 項目 | 主な科目 | 出題数 |
|---|---|---|
| (1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること | 区分所有法 | 12問 |
| マンション標準管理規約 | 8問 | |
| 民法、その他法令 | 6問 | |
| (2)管理組合の運営の円滑化に関すること | 管理実務 | 2問 |
| 会計 | 2問 | |
| (3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること | 建築、設備 | 15問 |
| (4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンション管理適正化法 | 5問 |
| 合計 | 50問 | |
試験日程
例年、11月の最終日曜日(第4又は第5日曜日)に実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、初心者がマンション管理士試験に合格するためには、500時間程度の勉強時間が必要と言われています。
1日に1~3時間の勉強時間なら、半年~1年程度が標準的な学習期間になってきます。
ただし、宅建試験の合格者なら、半分程度(250時間)の勉強時間で足りるのではないかと思います。(私も、約200時間の勉強時間で合格できました。)
難易度・合格率
受験者数は、約1万1千人で、合格率は10%程度で推移しています。管理業務主任者に比べても難関資格といえます。
No.4:行政書士
行政書士の資格を持っていれば、宅建業で不動産の取引をする際に、農地法の許可や各種営業の許認可を自ら申請できるようになります。
また、宅建試験で重要な科目である「民法」が、行政書士試験でも重要科目になっていることから、試験科目のうえでの親和性も高い資格と言えます。
行政書士とは
行政書士は、行政手続の専門家であり、「許認可のプロフェッショナル」です。国の管轄でいうと、「総務省」の管轄になります。
行政書士は、官公署に提出する許認可等の書類の作成やその手続の代理、権利義務又は事実証明に関する書類の作成などを、その業務としています。
資格の取得方法
行政書士になるには、行政書士になるための資格を取得してから、日本行政書士会連合会に登録するという2段階の手続きが必要になります。
行政書士になる資格を取得するための最も一般的な方法は、年に1回実施される行政書士試験に合格することです。
その他の方法としては、国家公務員、地方公務員又は一定の独立行政法人の職員として、行政事務に20年以上(高卒以上の学歴がある場合17年以上)従事することによっても、行政書士の資格を取得することができます。
また、弁護士、弁理士、公認会計士又は税理士のいずれかの国家資格を取得することによっても、行政書士の資格を得ることができます。
上記のいずれかの方法によって行政書士となる資格を取得した後に、各都道府県を通じて「日本行政書士会連合会」に登録することで、行政書士として業務を行うことができるようになります。
試験科目
令和6年度(2024年度)からの試験科目の変更について
2024年度(令和6年度)から、試験科目が若干変更され、これまで「一般知識等」と呼んでいた科目が「基礎知識」になりました。
「一般知識等」科目内の「政治・経済・社会」が「一般知識」になり、「行政書士法等の諸法令」が新たに明記されました。
| 令和5年度まで | ⇒ | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般知識等 | 政治・経済・社会 | 基礎知識 | 一般知識 | |
| 行政書士法等の諸法令 | ||||
| 情報通信・個人情報保護 | 情報通信・個人情報保護 | |||
| 文章理解 | 文章理解 | |||
法令科目:択一式(5肢択一式・多肢選択式)(マークシート方式)及び記述式(40字程度)
一般知識:5肢択一式(マークシート方式)
| 試験科目【法令等】 | 5肢択一式 | 多肢選択式 | 記述式 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 5問 | 1問 | - |
| 行政法 | 19問 | 2問 | 1問 |
| 民法 | 9問 | - | 2問 |
| 商法(会社法) | 5問 | - | - |
| 基礎法学 | 2問 | - | - |
| 合計 | 46問 | ||
| 試験科目【基礎知識】 | 択一式 |
|---|---|
| 一般知識 | 2023年度試験までの「政治・経済・社会」で出題されていた7問が2つの科目に割り振られるものと予想されます。 |
| 行政書士法等 | |
| 情報通信・個人情報保護 | 4問 |
| 文章理解 | 3問 |
| 合計 | 14問 |
試験日程
例年、11月の第2日曜日に実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、初心者が行政書士試験に合格するためには、500時間(~800時間)程度の勉強時間が必要と言われています。
1日に1~3時間の勉強時間なら、半年から1年半程度が標準的な学習期間になってきます。
ただし、宅建試験の合格者なら、重要な民法の科目が学習済みなので、4分の3~5分の4ぐらい(400時間ぐらい)が目安になるかと思います。(私の場合、さらに行政法についても実務経験がありましたので、約250時間で合格できました。)
難易度・合格率
受験者数は約4万人で、合格率は10%前後で推移しています。10%という数値は、高い難易度と言えます。
No.5:司法書士
司法書士は、宅建業と密接に関係する資格ですね。
司法書士の資格を持っていれば、不動産売買の際に、所有権移転や抵当権設定などの登記を自ら申請できるようになります。
試験科目としては、宅建で重要な科目「民法」が司法書士でも最重要科目ですので、その意味では、宅建で学んだ知識が活かせる資格でもあります。
司法書士とは
司法書士とは、弁護士のような敷居の高い法律家ではなく、「市民に身近な法律家」として活躍できる資格です。
司法書士の業務は、これまでは不動産登記・商業登記の「登記業務」が中心でしたが、法改正により、簡易裁判所の訴訟代理権が与えられ(認定司法書士)、弁護士同様に裁判業務もできるようになりました。
さらに、高齢化社会の進展により成年後見制度や民事信託などにおいても、活躍の場を広げています。
資格の取得方法
司法書士になるためには、年に1回実施される司法書士試験に合格した後に、各種の研修(中央新人研修、ブロック新人研修、配属研修、特別研修)を受講したうえで、司法書士会に入会し、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受ける必要があります。
試験科目
<筆記試験>
多肢択一式(マークシート方式)70問(午前の部:35問、午後の部:35問)、記述式2問
| 午前/午後 | 出題形式 | 試験科目 | 出題数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 午前の部 (9時30分~11時30分) 2時間 |
択一式 | 憲法 | 3問 | 35問 |
| 民法 | 20問 | |||
| 商法(会社法) | 9問 | |||
| 刑法 | 3問 | |||
| 午後の部 (13時~16時) 3時間 |
択一式 | 不動産登記法 | 16問 | 35問 |
| 商業登記法 | 8問 | |||
| 供託法 | 3問 | |||
| 民事訴訟法 | 5問 | |||
| 民事執行法 | 1問 | |||
| 民事保全法 | 1問 | |||
| 司法書士法 | 1問 | |||
| 記述式 | 不動産登記法 | 1問 | 2問 | |
| 商業登記法 | 1問 |
<口述試験(筆記試験合格者のみ)>
不動産登記法、商業登記法、司法書士法の3科目
試験日程
<筆記試験>
例年、7月の第1日曜日に実施
<口述試験(筆記試験合格者のみ)>
例年、10月中旬ごろ実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、司法書士試験に合格するためには、最低3,000時間の勉強時間が必要と言われています。
1日に3時間の勉強時間なら3年かかりますし、1日に6時間勉強したとしても、1年半ほどかかる計算になります。
司法書士試験に関しては、宅建試験の合格者というアドバンテージはあるにはありますが、トータルの勉強時間に大きな影響を及ぼすものではないと考えた方がよいかと思います。
宅建試験の重要科目である「民法」は、司法書士試験でも最重要科目ですが、そもそも3,000時間の勉強時間が必要とされる司法書士試験において、大差はないということです。(私も、合格には約3,000時間の勉強時間を要しました。)
難易度・合格率
受験者数は1万4千人程度で、合格率は4~5%で推移しています。非常に高い難易度です。
No.6:土地家屋調査士・測量士補
土地家屋調査士は宅建業に深く関わる資格です。
土地家屋調査士の資格を持っていれば、家を新築した場合や、分譲開発などで土地の分筆や地目変更をする場合などに、自ら登記申請ができるようになります。
ただし、土地家屋調査士試験は、民法や不動産登記法という共通科目もありますが、上記の不動産資格や法律資格とはガラッと毛色が異なる試験で、図面の作成や座標計算が試験の中心になりますので、挑戦する場合は注意が必要です。
なお、試験は午前の部・午後の部に分かれていて、午前の部は、測量士、測量士補、一級建築士又は二級建築士の資格がある方は免除となるため、例年、午前の部を受験する人は、ほとんどいません。
これら免除資格の中で最も取りやすく、かつ、土地家屋調査士の試験科目とも関連性の高い「測量士補」の資格をあらかじめ取得するのがおすすめです。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は、不動産(土地又は建物)の所有者に代理して、不動産の「表示に関する登記」手続を行うこと、及び、この登記手続に必要な不動産の調査や測量を行うことを主な業務とする資格です。
この「表示に関する登記」の手続代理は、土地家屋調査士だけが行うことができる独占業務とされています。
資格の取得方法
土地家屋調査士になるためには、1年に1回実施される土地家屋調査士試験に合格した後、各都道府県の土地家屋調査士会に入会し、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受ける必要があります。
試験科目
<筆記試験>
■ 午前の部【測量】
多肢択一式(マークシート10問)、記述式(1問)
※ 測量士、測量士補、一級建築士又は二級建築士の資格がある方は、午前の部が免除となります。例年、午前の部を受験する人は、ほとんどいません。
■ 午後の部【民法、登記申請手続・審査請求手続、その他】
多肢択一式(マークシート20問)、記述式(2問)
<口述試験(筆記試験合格者のみ)>
登記申請手続・審査請求手続、その他
試験日程
<筆記試験>
例年、10月の第3日曜日に実施
<口述試験(筆記試験合格者のみ)>
1月の後半に実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、初心者が土地家屋調査士試験に合格するためには1,000時間程度の勉強時間が必要と言われています。
1日に2~3時間の勉強時間なら、1年~1年半程度が標準的な学習期間になってきます。
土地家屋調査士試験に関しては、宅建試験の合格者だからといって、勉強時間が少なくて済むようなことはありません。
必要とされる知識が大きく異なりますし、どちらかといえば、記述式対策がメインになりますので、図面を書いたり、電卓で座標を求めたり、登記申請書を書いたり、といった問題演習が試験対策の大きな比重を占める試験です。(私も、合格には約1,000時間の勉強時間を要しました。)
ここには、午前試験(測量科目)の勉強時間は含まれていませんので、土地家屋調査士の午前試験の免除資格を保有されていない方は、別途、測量士補試験を受験するための勉強時間(約200時間)が必要となります。
難易度・合格率
受験者数は約4千人で、合格率は9%程度で推移しています。10%を切る合格率ですので、高い難易度と言えます。
No.7:ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)
FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金のエキスパートです。その知識に基づき、不動産取得資金の調達やライフプラン、不動産投資などのコンサルとして、お客様にアドバイスできるようになります。
このため、宅建業者で働く宅建士にとって、とても役に立つ資格と言えますね。
また、不動産や相続に関しては、宅建の試験範囲との重複もあります。
仕事に活かせるレベルは2級以上と言われていますので、以下では、2級FP技能士について記載していきます。
資格の取得方法
ファイナンシャル・プランナー(FP2級)の資格を取得するためには、2級FP技能検定試験に合格する必要があります。
2級FP技能検定には受験資格が定められていて、「3級FP技能検定の合格者」、「FP協会のAFP認定研修の修了者」、「FP業務に関する2年以上の実務経験者」、「金融渉外技能審査(旧 金財FP)3級の合格者」のいずれかに該当する必要があります。
試験科目(FP協会の場合)
学科試験(午前) CBT試験(四肢択一式 60問)
実技試験(午後) CBT試験(〇×式、四択式、多肢選択式、計算結果入力 合計40問)
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
試験日程
CBT試験に移行したため、随時実施
合格に必要な勉強時間
一般に、ファイナンシャル・プランナー(FP技能士2級)に合格するためには、200時間(150~300時間)の勉強時間が必要と言われています。
1日に1~3時間の勉強時間なら、3~6ヶ月程度が標準的な学習期間になってきます。
ファイナンシャル・プランナーの試験科目の中で、不動産や相続・事業承継に関しては、宅建の試験範囲との重複があるため、宅建合格者には有利ですね。(私も、相場よりやや少なめの130時間の勉強時間で合格できました。)
難易度・合格率
学科試験:40%程度
実技試験:50%程度
※ FP試験は「FP協会」と「きんざい」の2団体で実施されており、合格率に差がありますが、その2団体の平均合格率を記載しています。
No.8:社会保険労務士(社労士)
社労士(社会保険労務士)は、法律資格に分類されるとはいえ、ここまでに出てきた行政書士、司法書士などの法律資格とは毛色が異なる資格です。
社労士とは
社労士は、労働や社会保険、そして、人事や労務管理に関するプロフェッショナルで、「”人”に関する専門家」と呼ばれています。
お客様との営業の面では、大きな買い物をするにあたり、将来の年金や社会保険などの専門知識を備えていることは有利に働くことは間違いありません。
資格の取得方法
社労士になるためには、年に1回実施される社会保険労務士試験に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社労士名簿に登録を受ける必要があります。
この登録を受けるには、労働社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上あること、又は、事務指定講習を修了することが要件とされています。
試験科目
・選択式(マークシート)(午前) 8問
・択一式(マークシート)(午後) 70問
| 試験科目 | 選択式 | 択一式 |
|---|---|---|
| 労働基準法・労働安全衛生法 | 1問 | 10問 |
| 労働者災害補償保険法(徴収法を含む) | 1問 | 10問 |
| 雇用保険法(徴収法を含む) | 1問 | 10問 |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問 | 10問 |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問 | |
| 健康保険法 | 1問 | 10問 |
| 厚生年金保険法 | 1問 | 10問 |
| 国民年金法 | 1問 | 10問 |
| 合計 | 8問 | 70問 |
試験日程
例年、8月の第4日曜日に実施
合格に必要な勉強時間
一般的に、初心者が社労士試験に合格するためには1,000時間程度の勉強時間が必要と言われています。
この場合、1日に2~3時間の勉強時間なら、1年~1年半程度が標準的な学習期間になってきます。
試験科目を見れば明らかですが、宅建試験との重複はありませんので、宅建試験の合格者であっても、完全な初学者として勉強する必要がある試験です。(私も、合格には880時間の勉強時間を要しました。)
難易度・合格率
受験者数は約4万人で、合格率は6%前後で推移しています。かなりの難関資格です。
宅建からのダブルライセンス・トリプルライセンス【まとめ】
以上、宅建の資格を取った後に、ダブルライセンス・トリプルライセンスが狙える資格や役に立つ資格について紹介してきました。
最後に、一覧表に整理しておきますので、これを眺めながらダブルライセンス・トリプルライセンスを検討してみてください!
| 資格名 | 日程 | 出題方式 | 目安勉強時間 | 受験者数 | 難易度・合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務主任者 | 12月 第1日曜日 |
マークシート | 300時間 | 1万5千人 | 20%程度 |
| マンション管理士 | 11月 最終日曜日 |
マークシート | 500時間 | 1万1千人 | 10%程度 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 11月 第3日曜日 |
マークシート | 200時間 | 3万人 | 30%程度 |
| 土地家屋調査士 | 【筆記】 10月 第3日曜日 【口述】 1月後半 |
【筆記(午前)】※測量士補等で免除 マークシート 記述式 【筆記(午後)】 マークシート 記述式 【口述】筆記合格者のみ |
1,000時間 | 4千人 | 9%程度 |
| 行政書士 | 11月 第2日曜日 |
【法令科目】 マークシート 記述式(40字程度) 【基礎知識】 マークシート |
500~800時間 | 4万人 | 10%前後 |
| 司法書士 | 【筆記】 7月 第1日曜日 【口述】 10月中旬 |
【筆記】 マークシート 記述式 【口述】筆記合格者のみ |
3,000時間 | 1万4千人 | 4~5%程度 |
| ファイナンシャル・プランナー(FP技能士2級) | CBT試験のため随時実施 | 【学科試験】 CBT試験(四択式) 【実技試験】 CBT試験(○×式・四択式・多肢選択式・計算結果入力) |
150~300時間 | 年間18万人 | 学科:40%程度 実技:50%程度 |
| 社労士 | 8月 第4日曜日 |
マークシート | 1,000時間 | 4万人 | 6%前後 |