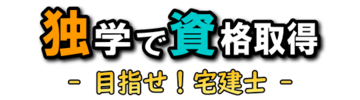宅建の試験内容は?科目ごとの対策や目標点まで徹底解説!
更新日:2025年1月24日
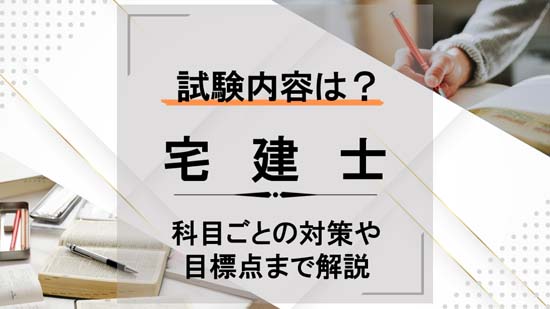
宅建試験の受験を考えている皆さんは、「どんな試験科目が出題されるの?」「どんな試験対策をすればいいの?」など気になっているのではないでしょうか。
そこで、このページでは、宅建の試験内容や科目ごとの対策・目標点について、解説したいと思います。
|
【執筆者】 |
執筆者紹介 |
宅建の試験内容
では、宅建試験の試験科目、出題形式・出題数などの試験内容について、解説していきます。
試験科目は大きく分けて4科目
宅建試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれており、その試験内容は、おおむね次のとおりと公表されています。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
公表されている試験内容は上記のとおりですが、実際に試験に出題される試験科目は、大きく分けて、①宅建業法 ②権利関係(民法等) ③法令上の制限 ④税・その他の4つの科目に分類することができます。
| 試験科目 | 試験内容 |
|---|---|
|
宅建業法 |
|
|
権利関係 |
|
|
法令上の制限 |
|
|
税・その他 |
|
四肢択一式で50問が出題される
宅建試験は、四肢択一式で50問(マークシート方式)が出題される筆記試験です。
ただし、登録講習修了者は試験の一部が免除され、45問のみの出題となります。
全ての出題がマークシート方式となっており記述式問題はありませんので、比較的試験対策をしやすい出題方式といえますね。
試験科目ごとの出題数は、次の表のとおりです。
| 試験科目 | 出題数 |
|---|---|
| 宅建業法 | 20問 |
| 権利関係 | 14問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 税・その他 | 8問 |
| 合計 | 50問 |
なお、試験問題については、試験実施機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」の公式サイトにて、過去3年分の試験問題と解答番号がPDFでダウンロードできるようになっています。(解説は付いていません) ⇒ 宅建試験の試験問題(過去3年分)
登録講習修了者は5問免除が受けられる
宅地建物取引業に従事し、「従業者証明書」を持っている方は、登録講習機関が実施する「登録講習」を受け、登録講習修了試験に合格して登録講習修了者証明書の交付を受けた場合は、修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅建試験において、一部免除(5問免除)を受けることができます。
この場合、試験時間は10分短縮されます。
登録講習というのは、2ヶ月程度の通信教育とスクーリング(2日間で計10時間の講義+修了試験)を受講する内容になっており、LEC、TAC、大原などの登録講習機関で受講することができます。(登録講習機関一覧(国交省ホームページ)。※受講料として、1~2万円程度の費用がかかります。
免除される5問は、試験科目の「その他」の部分で、問46~問50で出題される5問です。
科目ごとの対策と目標点
次は、宅建試験の試験科目ごとの対策や、目標とすべき得点について、お伝えしたいと思います。
宅建業法は最重要科目
まずは、宅建業法です。
宅建業法(宅地建物取引業法)は、宅地や建物の取引に関するルールを定めた法律です。
重要事項説明や37条書面(契約書)など、宅建士になってからの実務において直接的に必要となる知識が問われます。
出題範囲が狭いわりに出題数が最も多いため(全50問中20問)、最重要科目として得点源にすべき科目です。
権利関係は深入りせず効率的に
権利関係については、民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法から出題されますが、14問のうち10問が民法からの出題となっています。
民法は、他の法律系や不動産系の資格試験においても必ずといっていいほど試験科目に含まれる重要な法律です。
私たちの日常にかかわる法律ですのでイメージしやすいですが、出題範囲が広く、苦手とする受験生が多い試験科目です。
条文知識だけでなく様々な判例知識も含めて理解していく必要があるなど、非常に奥が深いため、民法で挫折してしまう人はかなり多いと考えられます。
このため、しっかりと時間をかけて学習する必要がありますが、得意科目にできてしまえば最強です。
ただし、なかなかそう簡単にはいかないと思いますので、深入りせず、いかに効率的に最低限の得点を稼げるかがポイントとなります。
法令上の制限はポイントを絞って暗記
法令上の制限は、土地や建物に関する権利を制限する法令からの出題です。
都市計画法や建築基準法、国土利用計画法、農地法など様々な法令から出題されます。
民法などの権利関係とは違って、日常生活ではあまり触れることのない法律を扱いますので、実務で経験していない人にとってはイメージがつきにくく、とっつきにくい科目といえます。
ただし、出題範囲を絞り込みやすく、暗記ものが多い科目ですので、ポイントを絞って暗記事項をしっかりと暗記するようにしましょう。
税・その他もポイントを絞って学習
税・その他では、税金に関する知識や地価公示法、不動産鑑定評価基準、統計・土地・建物など、幅広い知識が問われます。
出題範囲が広く、難易度の差が大きいため、誰でも正解できるような基本的な問題を落とさず正解できるように、ポイントを絞って学習することが重要です。
試験科目ごとの目標点 |合計38点を目指す
では、上記の試験科目ごとの対策を踏まえ、各科目の目標点を掲げると、下表のようになります。
| 試験科目 | 出題数 | 目標点 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 18点(90%) |
| 権利関係 | 14問 | 10点(71%) |
| 法令上の制限 | 8問 | 5点(62%) |
| 税・その他 | 8問 | 5点(62%) |
| 合計 | 50問 | 38点(76%) |
最も出題数が多く、得点源とすべき宅建業法については、満点を狙うつもりで点数を取りに行く必要がありますので、9割の18点が目標です。
次に出題数の多い権利関係については、高得点を目指すのは困難な科目ですが、出題数が多いため、7割程度の10点は欲しいところです。
法令上の制限と税・その他については、出題数は少ないですので、効率的に学習を済ませ、6割程度の5点ずつぐらいを確実に得点しておきたいですね。
宅建試験の合格点は、直近5年間では、低い年は34点ですが、最も高い年は38点ですので、合計得点は38点を目標に設定しておく必要がありますね。
宅建の試験内容まとめ
以上、宅建の試験内容や試験科目ごとの対策と目標点について、ご紹介してきました。
ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。
- 試験科目は、①宅建業法(20問) ②権利関係(14問) ③法令上の制限(8問) ④税・その他(8問)の4科目
- 出題形式・出題数は、四肢択一式(マークシート方式)で50問が出題される筆記試験
- 宅建業者に従事し、従業者証明書を持っている方は、登録講習の修了試験合格日から3年以内に実施される宅建試験で5問免除を受けられる。
- 宅建業法は、出題数が最も多い最重要科目。20問中18問(9割)が目標点
- 権利関係は、苦手とする受験生が多いが、2番目に重要な科目。14問中10問(7割)が目標点
- 法令上の制限、税・その他は、ポイントを絞って学習し、それぞれ8問中5問(6割)が目標点
- 合計得点の目標は、50問中38問(過去5年で最高の合格点)
以上、宅建試験の試験内容でした。
宅建試験は年に1度しかない一発勝負です。しっかりと準備して、合格を勝ち取ってください!
- 独学で合格を目指す場合はこちら⇒宅建の独学におすすめのテキスト
- 独学が不安な方はこちらへ⇒宅建通信講座おすすめランキング